矯正コラム
保定で使うリテーナーとは
「矯正治療で使うリテーナーってなに?」と気になっていませんか?
メインの治療後に使用する装置をリテーナーといいますが、その必要性や正しい使用方法についてくわしく知らないという方は実は少なくありません。リテーナーは矯正治療の最終段階に使用するものであり、後戻りのリスクを左右する大切な装置です。正しく使って納得のいく形で治療を終えるようにしましょう。
こちらのページでは、リテーナーの種類や痛みの有無、使用期間、正しいお手入れ方法などについて分かりやすくまとめました。矯正治療中の方はもちろんご検討中の方もぜひご参考ください。
目次
リテーナーの主な種類について
ベッグリテーナー
ホーレーリテーナー
QCMリテーナー
クリアリテーナー(マウスピースタイプ)
リンガルリテーナー
リテーナーは痛い?痛みが発生する主な原因について
リテーナーの装着時間や期間はどのくらい?
リテーナー利用中の通院頻度は?
リテーナーの料金は歯科医院によって異なる
リテーナーの正しいお手入れ方法について
リテーナーの洗い方
水につけっぱなしにしておくときの注意点
洗浄剤を使用するときの注意点
他院でリテーナーだけを作ってもらうことは可能?
リテーナー後の後戻りのリスクについて
定期検診は忘れずに
リテーナーの使用・管理方法に困ったら当院までご相談を
リテーナーについてのよくある質問
保定期間に使用するリテーナー(保定装置)とは?

メインの治療で整えた歯並びを一定期間固定するときに使用する装置を「リテーナー(保定装置)」といいます。歯は歯槽骨の吸収と再生を繰り返して動く仕組みですが、歯根の周囲にある歯根膜はゴムのように伸び縮みするため、歯槽骨の再生が終わるまでは不安定な状態が続きます。その間は後戻りのリスクが高いため、リテーナーを使って固定しなくてはいけません。正しい使い方をしっかり理解して、後戻りのリスクを最小限に抑えましょう。
リテーナーの主な種類について
使用するリテーナーのタイプは、もともとの歯並びの状態や管理能力などをみて適切なものを歯科医院側が判断します。歯科医院によって取り扱っているリテーナーは異なるため、心配な方は事前に確認しておくといいでしょう。
当院(新宿歯科・矯正歯科)では、マウスピースタイプ型のリテーナーを使用しています。そのほかのタイプも含めてどのような違いがあるのかを以下でくわしくみていきましょう。
ベッグリテーナー
歯列全体をワイヤーで覆うタイプのリテーナーです。ワイヤーで歯列全体を締め付けて歯がズレるのを防ぎます。
裏側(歯ぐきに触れる部分)はプラスチックでできており、取り外しが可能です。噛む面を覆わないため破損しにくいですが、ワイヤーが人目につきやすいという欠点があります。
主に抜歯を伴う症例でよく使用されます。
ホーレーリテーナー
ベッグリテーナーと似ている歯列をワイヤーで覆うタイプのリテーナーです。前歯部の後戻りを防ぐ効果があります。
取り外しが可能で、前歯部にのみワイヤーがないのが特徴です。
QCMリテーナー
ベッグリテーナーと同じ構造の歯列全体を覆うタイプのリテーナーです。
前歯部のみ透明なファイバーでできているため目立ちにくいのが特徴で、抜歯を伴う症例にも向いています。
クリアリテーナー(マウスピースタイプ)
歯列全体を覆うマウスピース型のリテーナーです。
見た目が透明で他のタイプよりも目立ちにくいのが特徴で、取り外しが可能なためお手入れや食事も今までどおり行えます。
噛む面を覆うため、食いしばりや歯ぎしりの癖がある方は注意が必要です。また、長期間の使用で変色する可能性があるので「毎日のお手入れを丁寧に行う」「定期的に洗浄剤を使う」などして対策をしましょう。
リンガルリテーナー
歯の裏面に固定するタイプのリテーナーです。
固定式で特別な管理が必要なく、正面からはほとんど見えません。
専用の接着剤で固定しているため、脱離した場合はすぐにつけ直しが必要です。また、装置の周囲に磨き残しがおこりやすく歯石がつきやすい点もデメリットといえるでしょう。放置すると虫歯や歯周病につながるため、丁寧なお手入れや定期的なクリーニングで予防することが大切です。
主に叢生の症例でよく使用されます。
リテーナーは痛い?痛みが発生する主な原因について
メインの治療のあとに使用するリテーナーは「歯の固定」を目的としているため、歯が動くことによる痛みは発生しません。リテーナーで痛みを感じるのは、後戻りが原因であるケースがほとんどです。装着時間の不足は後戻りにつながりやすく、場合によってはリテーナーが使えなくなることもあるため注意しましょう。リテーナーを正しく使用することが後戻りを防ぐ大きなポイントです。
リテーナーの装着時間や期間はどのくらい?

リテーナーの装着時間は、開始時は1日20時間以上で、状態をみて徐々に短くしていくのが一般的です。最終段階は夜間のみの装着となるので、それを目指して頑張りましょう。
使用期間はメインの治療と同程度もしくはそれよりも少し長めにするケースがほとんどです。装着時間・期間ともに患者様自身で判断して短くするのは、後戻りのリスクを高めます。かならず歯科医院側の指示どおりに使うようにしてください。
リテーナー利用中の通院頻度は?
メインの治療とは違って調整はありませんが、後戻りのリスクが高い初期は3か月に1回の通院が必要です。状態をみて徐々に間隔を延ばしていくので、その間にトラブルがおこらないよう定期メンテナンスはしっかり受けるようにしましょう。保定期間が2年の場合は、トータルで4回程度ご来院していただくことになります。
保定期間中はメインの治療と同じように装置があることで虫歯や歯周病のリスクが通常よりも高くなります。新たな詰め物や被せ物が入ると歯の形が変わって装置が使えなくなることもあるため、引き続き丁寧なお手入れを心がけましょう。
リテーナーの料金は歯科医院によって異なる
リテーナーに限らず自費診療であるものは、すべて設定金額が歯科医院によって異なります。矯正治療費にリテーナーの料金が含まれているケースも珍しくありません。別途かかる場合や作り直しが必要になった場合は、リテーナーの種類によって費用が異なるため、気になる方は事前に確認しておくといいでしょう。
(保定装置(リテーナー)再作製に関するご質問)
リテーナーの正しいお手入れ方法について
お口のなかの汚れは、使用するリテーナーにも付着します。ご自身の歯とは別にリテーナーも毎日洗う必要があり、それを怠ると変色や臭いがつくといったトラブルにつながるため注意しましょう。虫歯や歯周病のリスクも上がります。
リテーナーの洗い方
流水下で柔らかめの歯ブラシを使って汚れを落とし、定期的に専用の洗浄剤を使用して菌の増殖や変色を防ぎます。
多くのリテーナーでお湯の使用は禁止されており、リテーナーの種類によっては強すぎる流水や長期間水につけておくだけでも変形のリスクがあります。受け渡しのときに伝えられる管理方法は正しく理解しておくようにしましょう。
水につけっぱなしにしておくときの注意点
お湯ではなく水もしくはぬるま湯を使用する
お湯に触れると装置が変形する可能性があるため、かならず水もしくはぬるま湯を使うようにしてください。変形した装置を使うのは歯並びが崩れる大きな原因です。歯科医院に連絡して作り直してもらいましょう。
使用する水は毎日取り替える
歯ブラシを使って磨いても、リテーナーに付着した菌をゼロにはできません。一度使用した水のなかには菌が含まれているため、使いまわすのは不衛生です。面倒でも毎回取り替えるようにしましょう。
長期間水につけていいタイプかを事前に確認しておく
リテーナーの種類によっては長期間水につけておくと変色や変形につながるものもあるため注意が必要です。トラブルを最小限に抑えるためにも、使用するリテーナーの管理方法は正しく理解しておくようにしてください。
洗浄剤を使用するときの注意点
リテーナー専用のものを使用する
洗浄剤にも種類があり、専用のものでない場合は変色や変形といったトラブルにつながる可能性があります。とくに市販のものを使用する場合は注意が必要です。心配な方は一度歯科医院に確認してから購入するようにしてください。
使用時間を厳守する
洗浄剤の使用時間は商品によって異なり、短すぎると効果が半減し、長すぎると変色や変形といったトラブルにつながる可能性があります。かならず使用方法や注意書きを確認したあとに使うようにしましょう。
同じ液を使いまわさない
殺菌効果のある洗浄剤であっても液の使いまわしは不衛生で、効果が半減する原因でもあります。水につける場合と同じように毎回取り替えるようにしましょう。
他院でリテーナーだけを作ってもらうことは可能?
歯科医院によって対応は異なりますが、当院では治療中でない患者様のリテーナー製作も承っております。紛失や破損などでお困りの方は一度ご相談ください。
マウスピース型リテーナー以外は取り扱っておりませんので、場合によっては使用する装置の変更が必要です。
リテーナー後の後戻りのリスクについて
歯が移動した先で安定したら矯正治療は終了となりますが、口周りの癖や頬杖・うつ伏せ寝など歯並びや噛み合わせに影響する癖が残っていると、再び崩れる可能性があります。メインの治療中にそれらの改善を合わせて行うと、後戻りのリスクを最小限に抑えるのでおすすめです。しかし、癖は自覚がない場合も多く、食いしばりや歯ぎしり以外の癖を歯科医院で発見するのは難しいといえます。歯並びや噛み合わせに影響しやすい癖を理解して、可能であればパートナーやご家族に普段癖がでているかどうかを確認してみましょう。
定期検診は忘れずに
矯正治療後の虫歯や歯周病が原因で、再び歯並びや噛み合わせが崩れるケースは少なくありません。治療を一からやり直す必要がでてきますが、それを避けるにはトラブルがおこる前の予防を意識することが大切です。
歯科医院の定期検診では、虫歯や歯周病のチェックのほかに、予防に役立つクリーニングやブラッシング指導も行っています。後戻りのリスクを最小限に抑えるためにも、定期検診をぜひ習慣化してください。
リテーナーの使用・管理方法に困ったら当院までご相談を
リテーナーは、メインの治療で整えた歯並びがしっかりと安定するまで一定期間固定しておくための装置です。種類によって取り扱い方法が異なり、間違った使い方をすると装置の変形や後戻りのリスクを高めるため注意しなくてはいけません。リテーナーを正しく使うことが矯正治療をスムーズに終わらせる大きなポイントといえるでしょう。
当院では、マウスピース型リテーナーを取り扱っております。目立ちにくく発音や滑舌にも影響しにくいリテーナーをご希望の方はお気軽にご相談ください。紛失や破損などでリテーナーを作り直したいという方からのご相談も承っております。


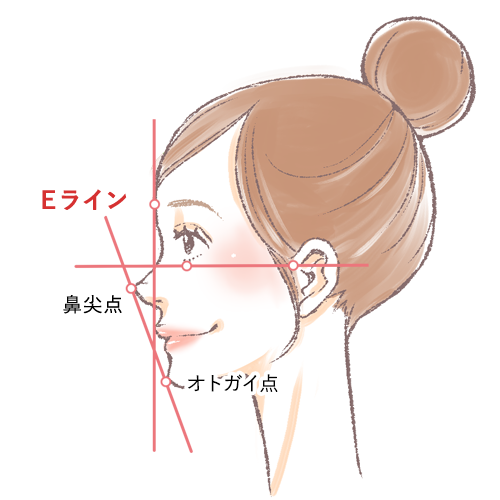


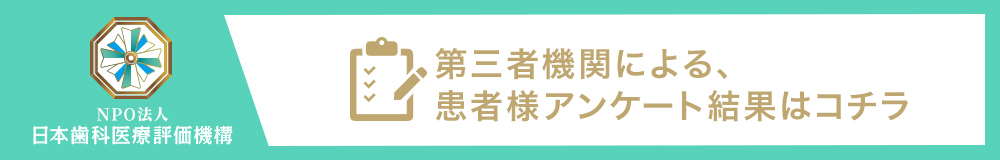
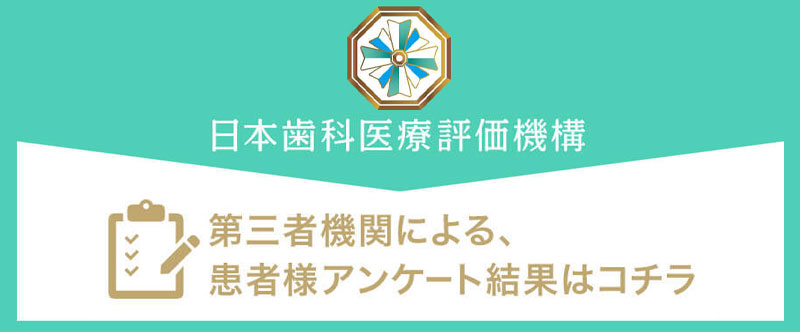
 治療ガイド
治療ガイド